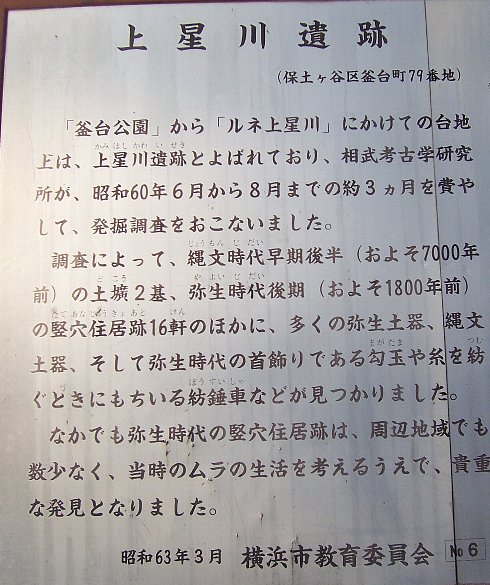保土ヶ谷情報
保土ヶ谷区の名前は東海道の「程ヶ谷宿」の名残りと思われます。
旧東海道は現在の松原商店街を通り、天徳院の前を通り保土ヶ谷税務署の西側を通っていました。
大門通りには旧東海道の石碑が建っています。松原商店街辺りは海も近く、松原があったので今に松原の名前が残ったといいます。
また国道1号線では一里塚松を植えて復元整備が進んでいます。旧保土ヶ谷本陣も、未だに門を保存・維持していて子孫の方も健在です。
この他国道16号線(八王子街道)が保土ヶ谷区を縦貫しています。16号線を稀にマッカーサー道路という古老がいます。
マッカーサーが厚木から来るので、真っ直ぐな道路を造ったということです。
両郡橋の名前の由来
知る人ぞ知る桜の名所が両郡橋…。帷子川の川面の上に、長く延びた桜の枝に春になると、ピンクの桜花がたわわに咲き乱れ、そよ風に揺られる情景は見ごたえがある。
桜の花は青空に映え、花の下を流れる浅い清流の水音とあいまって、自然と癒され心も和んでくるよう。
この桜の季節には、日本人であることの幸せが改めて思い起こされ、自分はやっぱり日本人なんだと自覚も蘇ってくる。
さて「両郡橋」のちょっと変わった名前の由来であるが、昔この場所は郡境だった事により名付けられたと言われている。
上星川駅から3分ほどの通称「水道道」の、帷子川に架けられているこの橋の名前を知っている人は少ない。
歩いて渡れば、6~7歩で通り過ぎてしまう事もあるのだろう。橋の袂にある両郡橋交番のなまえから、かろうじて橋の名前と推測している人もいるかもしれない。
昔、両郡橋より和田町側は橘樹郡坂本村と呼ばれ、両郡橋より西谷よりは都筑郡上星川村と呼ばれていた。
この両郡橋を境に郡名が変わることから「両郡橋」と呼ばれるようになり、今に至っている。
いま仏向町に「橘中学」があるが、これは橘樹郡の名残りであろうと思われる。仏向町なら通常は、仏向中学と名前が付きそうなものであるが、そうはなっていないことにより古い郡名の名を残したものと推測が成り立つ。
また一説によると、橋よりも和田町側が橘樹郡保土ヶ谷村で、橋よりも西谷側が都筑郡西谷村であったとする人もある。
この村名のどちらが正しいのかは、郷土史の文献をめくるか、明治の古地図を調べる必要がある。或いは時期によって村名が変わったものか。?

横浜の水道は日本で最初の近代水道
かっての横浜は小漁村で殆どが山であったトカ...?
明治の頃はナント僅かに87戸です。
今は300万を超えて日本第二の大人口...なのに信じられますか?
明治の頃の日本の人口は約3,500万人ですから、今のおよそ3分の1です。
8,000万人位になれば、渋滞もラッシュもなくなって暮らしやすくなるかも知れません。
さて、この寒村に近代水道を敷設したのは明治20年。日本で最初の水道です。
水源は津久井町(旧三井村)、今の津久井湖がある所です。
ここから横浜の野毛山に向かって、真っ直ぐの道路を造り資材を運んだ。
当時は車がなかった為に、まず線路を敷いてトロッコを走らせた。
この道に沿って導水管が埋設され、その道には今も「水道道」の名前が残っている。
英国人技師の協力を得て、この2年に及んだ水道工事は完成した。この水道道は武蔵国と相模国の境界付近に位置していた。
古地図にはまだ都筑郡と橘樹郡の名が残っている。
いま西谷に広い浄水場があり、敷地の中央に建つ水道記念館には様々な物が展示されている。

いよいよ、西谷駅から相鉄線がJR線に繋がる。
相鉄線を利用して都内へ行くには横浜駅を経由して行く。
これからは、西谷駅から線路が左に別れてJR羽沢駅に入り、そこから京浜東北線や横須賀線に繋がって行く。
今のJR羽沢駅は広い構内を持っている貨物線専用の駅。この駅の地下に相鉄線のホームが新設される予定。
事業は6年後に終結し、平成27年4月には開業予定。更に数年後には新横浜駅を経由して新綱島駅、日吉駅へと東横線とも直通になる予定。
相鉄線から渋谷や新宿にも直通電車が走ると言われている。二俣川あたりの人には非常に便利となる。
しかし西谷駅近辺の人たちは、本当に西谷駅に電車が停るのか心配している。
素通りされるだけなら何のメリットもなく?数軒の立ち退きも求められており、騒音などに困ってしまうだけ。


保土ヶ谷区にも古墳があった
瀬戸ヶ谷町の台地上に、かって存在した古墳はかなり大きな前方後円墳でその規模は横浜でも屈指のものである。この古墳の存在は近在の人々の間では知られていたというが、発見されたのは昭和18年という。
場所は保土ヶ谷橋のほど近く、現在の瀬戸ヶ谷町第二公園の西側で保土ヶ谷本陣の南側の台地である。地主の軽部三郎氏が耕作中に埴輪を発見したとされる。同名の保土ヶ谷本陣家は近辺に広大な土地を所有していたことから、本陣家の土地であった事が想定される。
昭和24年頃宅地開発の計画が提示され、初めて正式の調査をした模様。後円部は西に向いており、全長は約41mと近隣には類を見ない大きさである。その築造時期は6世紀と見られている。
これまでに墳丘から人物埴輪のほかに動物埴輪や家形、盾、刀、靱(ゆき)などが出土している。現在は丘陵地の住宅街に姿を変えていて、その昔この場所に古代の古墳があったとは思いも及ばない。
釜台町の保土ヶ谷中学にも古墳があった。ここには円墳が6基確認されている。
昭和32年に調査された後に破壊され学校の敷地となった。築造年代は古墳時代後期のものとされており、瀬戸ヶ谷古墳とは形状も全く違うものの築造年代はそう離れてはいないと思われる。
保土ヶ谷中学の北側に隣接する上星川遺跡では、三世紀ころの竪穴住居跡・16軒が発見されている。ここは現在釜台公園として整備されている。
仏向町は広いエリアにまたがっているが、橘中学の西側にも古墳が一基あった。この古墳は仏向神塚古墳と呼ばれている。釜台町の古墳と同じ円墳であり、築造年代は古墳時代初期のものと推定されているが、或いは中期にまで降るのではないかとも思われる。
同古墳は昭和52年に調査され、円墳の直径は23mで高さは2m。古墳の周囲には幅1.4m深さ0.4~0.8mの溝(濠)が掘られていた。調査により首飾り用と思われる玉類・鉄板片・土師器などが出土している。
尚、仏向団地では縄文時代から古墳時代にかけての集落跡や方形周溝墓が確認されていて、この地域に古くから長期間にわたって人が住んでいたことが判明している。
この他、区外にはなるが横浜駅西口にほど近い、軽井沢にも古墳があった。現在の関東自動車学校の敷地・南側周辺がそれである。全長約27mの前方後円墳で、築造年代は七世紀とされている。
以上見て来たように、保土ヶ谷の古墳はいずれも台地上に形成・築造されていた。
帷子川や今井川の水を飲用や水運・漁に利用していた事が窺われる。
いずれも、現在では学校などに姿を変えていてその面影は残されていない。

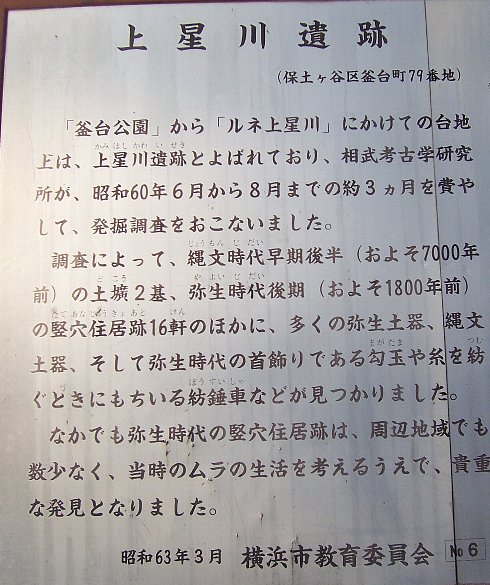

歴史を散歩 https://www.city.yokohama.jp/me/hodogaya/midokoro/rekisi/
保土ヶ谷区学校 https://www.city.yokohama.jp/me/hodogaya/kids/about/a04.html
保土ヶ谷区役所 https://www.city.yokohama.jp/me/hodogaya/